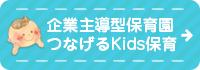- TOP
- 育児担当保育とは
育児担当保育とは
特定の保育士が、特定の子どもの育児(食事・排泄・睡眠)を一貫して丁寧に行うことで、乳児期における愛着関係を形成する保育です。
子ども一人ひとりの人格をありのまま受け入れ尊重し、自己肯定感を養うことで、子どもの能動性・社会性を引き出し、主体性を育むことで生きる力を養うことを目的としています。
乳幼児期に育まれる「他者への信頼」と「自己肯定感」
乳幼児期は、人生の土台を築く大切な時期です。 この時期に、人との関わりの中で「信頼感」を育むことは、やがてその子どもの「自己肯定感」へとつながり、これから先の人間関係や、生きる力に大きな影響を与えると言われています。
私たちの園では、一人ひとりの子どもに対して「担当保育士」がつきます。決まった大人が日々の生活を共にすることで、子どもは安心し、その大人との間に深い信頼関係や愛着を築いていきます。この関係性があるからこそ、子どもは「自分は愛されている存在なんだ」と感じることができ、それが心の安定と成長につながります。
こうした安心できる関係を土台にして、子どもは少しずつ信頼の輪を広げていきます。最初は特定の大人との絆から始まり、やがて周囲の人や環境にも安心感を抱けるようになります。園全体が子どもにとって「安心できる基地」となり、そこを拠点に自らの興味を広げ、主体的に学び始めます。
また、担当保育士が子どもの発達やその時々の心理的な状態を深く理解しながら丁寧に関わることで、基本的な生活習慣も自然と身についていきます。
私たちは、乳幼児期のこのかけがえのない時間を、子どもが「愛されている」と実感できるような温かい関係性の中で過ごせることを何よりも大切にしており、その方法の一つとして、「育児担当保育」に取り組んでいます。

育児担当保育に基づく園での生活
保育の基本
保育者(大人)の役割は、何かを直接子どもに教え込むことではなく、子ども自身が持っている個性を十分に引き出し、自らの考えを発揮し行動できるように援助することにあります。 よって、子ども一人ひとりの人格をありのまま受け入れ尊重することから保育が始まります。子ども自身の興味や発達段階を正しく理解し、やってみたいと思う環境を適切に用意し、子どもの主体性を促す保育を実施します。
4つの特徴
1.特定の大人による生活行為の援助
育児の部分(食事・排泄・睡眠)に関わる部分の援助を、特定の大人(担当保育士)が行うことで、愛着・信頼の関係を築きます。 特定の大人への信頼感が育つと、環境やその他の人も信頼し、安心感を得ることで子どもは自然と主体的に学ぶようになります。
2.流れる日課
毎日ができるだけ同じように繰り返されるように、おおよその時間や活動の流れを決めます。個々の生活に対応して、子どもが不必要に待つ時間があったり、子どもの遊び・行為が中断されたりすることがないように日課を設定します。この日課によって、子どもは見通しをもって行動できるようになり、落ち着いて日々を過ごすことができます。
3.遊び
子どもたち一人ひとりが好きなときに、好きな遊びを選択できるように、遊びをコーナー分けしています。 子どもたちは、遊びの中で物の扱い方や友達との関わり方、約束事などを学んでいきます。 子どもたちがたっぷり遊びこめる時間、じっくり遊びこめる空間、子どもの発達段階に応じた玩具を整え、より良い環境を提供します。
4.家庭的な環境づくり
保育園は第二の家庭と位置づけ、家庭と同じように安心して落ち着いて過ごせる環境づくりを行っています。 当園では保育士を「先生」ではなく、「○○さん」の呼称を使用しています。
園での過ごし方
へや遊び

遊びの主体は子どもたちです。大人は遊びのサポートをしています。子どもたちが自ら活動したいと思えるような環境を作り出し、試みるための十分な時間を提供し、自らが主体的に活動したいと思えるように働きかけ、子どもに現れる変化に気づき、支持し、要求にあった援助をします。
食事

0歳児
一人で歩ける頃までを目安に、担当保育士の膝の上で抱いて1対1で食事をします。
1歳児/2歳児
2~3人ずつ、担当保育士が介助しながら食事をします。「自分で」の自立した気持ちを大切にし、関わっていきます。
また、お友達と一緒に食べることで、食べる楽しさも味わっていきます。
睡眠

体をいっぱい動かして、ごはんでお腹いっぱいになると眠たくなる・・・というような自然な欲求の中で、自分のいつも決まったベッドの場所に向かいます。
いつもリズム、同じ場所、そしてそばに担当保育士がいると安心して眠りにつきます。
排泄
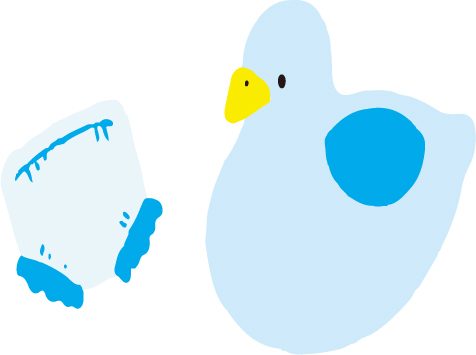
一人ひとりの排泄時間を知り、個々にあった援助を行います。
担当保育士が1対1で対応し、いつも同じ手順であることで安心感を育みます。
育児担当保育 Q&A
Q1.年度途中に担当が変わることはありますか?
基本的にはありません。 新入園児が入るなど、必要に応じて編成をすることがあります。子どものために変えることがあっても、保育士都合で編成を変えることはありません。
Q2.担当が休みの日はどうなりますか?
必ず決まった副担当がおり、担当が休みの日は副担当が育児を行います。 担当が休みであること、代わって副担当が育児をすることは、事前に子どもに伝えます。
Q3.保育士全員が子ども全員のことを把握できないのでは?
担当が行うのは育児の部分のみです。そのほかの時間は、全ての保育士で全ての子どもと関わります。 育児についても、日々の申し送りなどで職員全員で共有する時間を設けています。
Q4.「先生」呼びをしないのはなぜ?
「先生」というのは、「何かを教えてくれる人」、「高い技量や知識を持つ人」に対する敬称であり、 先生と生徒は、教え教えられる関係、評価し評価される関係です。 園は子どもにとって家庭に代わる生活の場であり、保育者はお母さん、お父さんに次いで、子どもにとって身近な存在でありたいとの願いから、私たち保育者は「○○先生」ではなく、「○○さん」の呼称を使用しています。